石原小のみなさん、
5月16日は
開校記念日です。
石原の誕生日です。
本日は、
石原小学校の歴史について紹介します。
なんと石原小学校は
明治6年石原村東西2字に各小学校を設立し
明治25年5月16日に熊谷町外1カ村組合立第2区石原尋常小学校として
独立したそうです。この
日を記念として、
開校記念日としたそうです。
明治35年に
石原小学校中央校舎落成(石原南裏)したそうです。

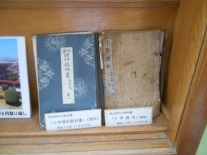 明治35年の石原小学校 明治時代の教科書
明治35年の石原小学校 明治時代の教科書
大正5年に高等小学校を併設、校名を
石原尋常高等小学校と改称したそうです。
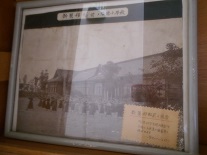 大正5年の女子ダンスの写真
大正5年の女子ダンスの写真
昭和47年火災のため
、第2校舎、第3校舎が24教室が
消失してしまったそうです。

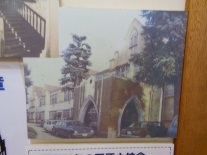
昭和
54年の木造校舎
昭和55年水泳用プール竣工しました。
平成4年第
3号棟全面改修しました。
平成9年に
石原ホームページを開設しました。
平成22年に
体育館を竣工をしました。
平成29年に石原小キャラクター
「いしわラッコ」児童のアイディアで完成。

 職員玄関にあるいしわラッコ 石原小の航空写真
職員玄関にあるいしわラッコ 石原小の航空写真
平成30年、
3号棟の大規模改修工事、東側フエンス改修工事をしました。
令和元年、トイレ改修工事、北川、西側フエンス改修工事をしました。
今現在から数えると
148年の歴史があり、熊谷市であは、熊谷東小学校 熊谷西小学校、成田小学校、大幡小学校などと並び
一番長い歴史のある学校となります。
新しいことにもたくさん挑戦しています。そんな素敵で伝統のある石原小学校をこれからもみんなで大切にしていきましょう。そして
これからの歴史を作っていきましょう。引き続きホームページの活用をお願いします。
新型コロナウイルス対策を含め
学校ホームページやすぐメールはこれからの学校においては
大きな役割を果たしていきます。
※変更等はメール、ホームページで再度の確認をお願いします。